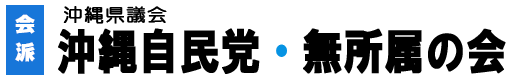弁明書提案理由説明 / 宮里洋史
令和7年5月16日
令和7年第3回沖縄県議会(臨時会)がおこなわれ、提案者を代表して宮里洋史議員が、議員提出議案「地方自治法第 258 条第1項において準用する行政不服審査法第 29 条第2項の規定に基づく弁明書」について提案理由を説明いたしました。

本案は、令和7年4月14日付総財第34号で沖縄県知事から総務大臣宛て提出された審査申立書に関し、地方自治法第258条第1項において準用する行政不服審査法第29条第2項の規定に基づき同年5月8日付文書で代表自治紛争処理委員から弁明書の提出を求められたことから、同規定により弁明書を提出するためのものであります。
次に、本案の概要を説明するのでありますが、内容が多岐にわたりますので、ポイントを絞ってご説明を致しますので、詳細は案文をご参照願います。
まず、去る令和7年2月議会において、令和7年度沖縄県一般会計予算及び令和7年度沖縄県公債管理特別会計予算に関して、借換債を58億円増額し、財政調整基金に積み立てる修正案が提出され、議会として予算を修正議決したことに対し、知事から地方自治法第176条第4項に基づき再議書が提出されましたが、議会において先の議決のとおり決しました。
以下の説明において、この議決を「本件議決」と呼ぶことと致します。
これに対し、知事は本件議決が知事の予算編成権を侵すものであり、議会の議決がその権限を超え又は法令に違反するとして、総務大臣に審査申し立てを行いました。
本案は地方自治法第258条第1項において準用する行政不服審査法第29条第2項の規定に基づく弁明書であり、審査申し立てに対して、議会としての見解を明らかにするものであり、知事の主張に対し、項目ごとに争うもの、争わないものを示しております。
基本的に、法令や通知の引用、事実関係に関しましては争わないこととし、本件議決に関する知事の認識や法令の解釈適用等、本件議決の趣旨を否定する見解に対しては、争うこととしております。
そして結論において、本件議決については予算の趣旨を損なう増額修正に当たらないことは明らかであって、長の予算の提出権限を侵すものではなく、地方自治法第97条第2項により認められた議会の予算修正権の範囲を超えるものではなく、本件議決は適法になされたものであって、申立人の主張はその理由を欠くものであり、本件申立ては棄却されるべきものである、としております。
次に、本弁明書における主たる見解を申し述べます。
弁明書の1ページ、第3の1、「第2の1(1)エ」についてであります。
知事は審査申立書において、「地方制度調査会の「人口減少社会に的確に対応する地方行政体制及びガバナンスのあり方に関する答申」において、「予算については長に提案権が専属していることから、議会による予算修正権の拡大については慎重に検討していくべきである。」とあり、議会の修正権は厳格に解されている。」と主張しております。
しかしながら、申立人が引用する地方制度調査会の答申については、地方自治法改正に関して将来に向けた意見であって、答申当時に存在していた地方自治法第97条第2項の解釈及び運用について述べたものではないことは明らかであって、申立人の主張は失当であります。
次に、同じく弁明書1ページ、第3の2(1)及び(2)、「第2の2(1)イ」及び「第2の2(1)ウ」について、であります。
知事は審査申立書において、「借換債は、年度ごとに発行可能額が異なり、恒常的な財源としては安定しないため、後年度に継続する事業の財源とするには課題がある。」「本件議決は、「本来、事業に充てることのできるキャッシュをみすみす取り逃している」とのことで、借換債を増額し、財政調整基金に積み立てるものとなっているが、具体的な事業の必要性や所要額の議論がない中で、後年度における財
源確保のみを目的として地方債を増やす手法であり、修正の必要性・相当性を欠いている。」と主張しております。
しかしながら、借換債を後年度に継続する事業の財源とするのかどうかは、まさに長の判断に委ねられているのであって、本件議決は特定の事務事業の財源に充当せよという内容ではなく、後年度の財政運営も考慮しつつ、長において適切な予算措置を行うために、財政調整基金へ積み立てるという趣旨であります。
また、具体的な事業の必要性や所要額の議論は予算編成権を有する長が行うべきものであって、こうした議論を反映させて個別具体の事務事業の財源を修正することこそ、長の予算編成権を侵すことにつながるものであり、したがって、議会としては本件議決において後年度の財源として活用可能な財政調整基金への積み立てを行うこととしたものであります。
次に、同じく弁明書1ページから2ページ、第3の2(3)及び(4)、「第2の2(1)オ」及び「第2の2(1)力」について、であります。
知事は審査申立書において、「借換可能額266 億円のうち、臨時財政対策債に相当する部分は165億円である。原案の173億円を臨時財政対策債とそれ以外の県債との借換可能額の比率で按分して推計した額107億円と、165億円との差額58億円が増額された。
しかし、借換債の内訳(臨時財政対策債とそれ以外)については、金融機関との交渉の結果、借換時に決まるものであり、臨時財政対策債相当額として算出した推計は、合理性を欠いている。」「常任委員会の審査の過程で生じた疑義について、改めて質疑を行う令和7年3月18日の予算特別委員会の総括質疑では取りあげられることなく、同月25日の予算特別委員会の採決に先立ち修正案が提出された。以上
のことから、長と議会との間で調整を行い、妥当な結論を見出したとは言い難い。」と主張しています。
しかしながら、本件議決の趣旨は、一般財源に相当する臨時財政対策債を優先的に借り換えるよう求めるものであって、借入金融機関との交渉においてもこうした観点を期待するものであります。しかしながら、原案の173億円を積算するに当たって、臨時財政対策債を何割程度借り換える考えを持っているのかについて、執行部は明確な答弁を行っておらず、執行部の議会に対する説明不足は否めません。したがって、予算審議の過程において173億円の積算根拠自体に合理性を見いだすことはできなかったわけであります。
こうした経緯から、案分によって相当額を算出するという方法を行ったのであり、積算方法として合理性や相当性を欠くものではありません。
また、臨時財政対策債の借換えについては、これまで幾度となく議会と長との間で議論が交わされてきたことは事実であり、総括質疑において取り上げられなかった一事をもって調整がなされなかった
と指摘することは失当であります。
事実、令和7年2月定例会中、本会議や委員会の場以外で、財政課担当者や総務部長との間で、「沖縄自民党・無所属の会」会派は、少なくとも2回は意見交換を行いました。
その際、こうした財源の活用方法についても検討していきたいとの発言も執行部側からあり、こうした一連の経緯を踏まえて本件議決に至ったのであり、申立人の主張はこうした事実経過を無視するものであります。
次に、同じく弁明書2ページ、第3の4(2)、「第2の2(3)エ」について、であります。
知事は審査申立書において、「原案における財政調整基金残高約71 億円は、前年度と同規模となっている。令和6年度においても様々な補正予算に対し、残高が不足することなく適切に措置していることから、今後の事情変更による財政需要に十分に対応できるものと考えており、地方債を増やしてまで財政調整基金を積み増す理由に欠ける。」と主張しております。
しかしながら、財政調整基金については、近年多発する災害対策や公共施設の維持•更新等、これまで以上に一定の規模を確保していく必要性が高まってきているのでありまして、こうした対応への財源を確保しつつ、これまで財源不足を理由に手当てできなかった事務事業の財源を見いだすという本件議決の趣旨を申立人は考慮しておりません。
次に、同じく弁明書2ページから3ページ、第3の5(1)、「第2の2(4)イ」について、であります。
知事は審査申立書において、「これまで、歳入不足を補う地方債である臨時財政対策債の借換えについては、必要な事業の財源を確保した上で、一部を繰上償還し将来の県民の利子負担の軽減を図りつつ、健全な財政運営を行ってきた。」と主張しています。
しかしながら、沖縄県は臨時財政対策債の制度創設以来、毎年度発行可能額満額の借入れを行っております。そして平成22年度頃から恒常的に借換え予定債の一部を繰上償還することによって、当該年度の当初予算編成時における収支差をコントロールする手法を取り入れております。
しかしながら、そもそも一旦借入れを行うことによって、5年ないし10年の利払いが発生しており、明確に県民負担が生じているのであります。
収支差を調整する必要があるのであれば、一般財源である臨時財政対策債の発行を一部取りやめるというのが、借換え時点までの利払いが発生しないという点で合理的であり、申立人の主張する健全な財政運営がなされてきたのかについては、疑問があります。
次に、同じく弁明書3ページ、第3の5(2)及び(3)、「第2の2(4)エ及びオ」について、であります。
知事は審査申立書において、「県債の借換えは、将来の財政需要や将来世代への負担などを熟慮して実施しており、本件議決により、直近の金利で試算すると約5億円の負担増となり、昨今の金利上昇傾向を踏まえると、今後更なる利子負担の増が見込まれる。」
「地方財政法第4条の2で「当該年度のみならず、翌年度以降における財政の状況をも考慮して、その健全な運営をそこなうことがないようにしなければならない。」と規定されており、当該条項は、長期的視野における地方公共団体の財政運営に関する基本原則を定めている。本件議決は、この原則を否定するものである。」と主張しております。
しかしながら、後年度の利息負担が約5億円増えることから将来負担を何ら考慮していないという申立人の主張については、基金に積み立てられた58 億円のうち5億円を利払いに充て、残りの53億円を他の必要な事務事業の財源として確保することができるという視点に欠けており、合理性のない主張であります。
また、修正案の提案理由説明にもあるとおり、実質公債費比率や将来負担比率という中長期的な財政指標への影響も加味したうえで本件議決はなされており、地方財政法第4条の2に反するという申立人の主張はあたらないものであります。
最後になりますが、弁明書4ページ、第3の6(3)、「第2の2(5)エ」について、であります。
知事は審査申立書において、「将来の世代への財政負担を含めた財政運営は、最終的に知事が責任を負うことになる。そのため、原案については、各部局が関連団体との意見交換等を踏まえ予算要求を行い、様々な観点から議論及び検討を行うことにより、必要な事業に対して所要額を精査し、適切な財源を確保した上で、編成している。本件議決が認められることになれば、後年度の財政負担の責任が不明確になる。」と主張しております。
しかしながら、議会を構成する議員は、それぞれの選出選挙区を中心に、日頃から多くの有権者や各種団体からの要請・陳情を受け、行政に対して取組を促す役割を果たしております。
こうした取組が長の予算編成過程において取り込まれることもあれば、そうでない場合もあり得る実情はありますが、議会における予算審議を通じて、こうした要請・陳情を踏まえた編成がなされているかを議論することが議会に求められている重要な機能の一つであることを鑑みれば、執行部内における予算編成過程に議会が関与していないという事実をもって、議会による予算の増額修正が後年度の財政負担の責任を不明確とするという指摘を行うことは、すなわち地方自治法第97条第2項に定める議会の予算修正権を否定するものであって、全くもって許し難い見解であります。
以上が本弁明書における主たる見解となります。