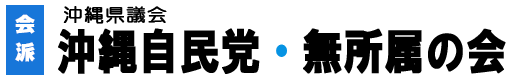[代表質問] 喜屋武力 令和7年第5回沖縄県議会9月定例会
令和七年9月18日(木)
第5回沖縄県議会(9月定例会)の代表質問に沖縄自民党・無所属の会より喜屋武力議員が2番手に立ちます。以下の質問項目を事前通告いたしました。

1:知事の政治姿勢について
(1) 県内の物価高騰は県民生活を直撃しており、特に食料品や光熱費の負担が家計を圧迫している。輸送費や物流コストが高い沖縄では、全国以上に影響が深刻である。こうした状況を踏まえ、県として物価高の現状をどう分析しているのか。さらに、国の補助施策に加え、県独自の支援策をどのように講じて県民生活を守るのか伺う。
(2) 令和8年度の沖縄振興予算概算要求は、人口減少や地域格差解消に直結する重要な政策手段である。県はこれまでの振興予算の執行効果をどう検証し、国に対してどのような重点要求を行っているのか。特に、離島振興や子育て支援、産業育成などにどのような予算配分を求めているのか。具体的な方向性と知事の考えを伺う。
(3) 県は「地域外交」を掲げて海外自治体との交流を推進しているが、具体的な成果が県民生活に直結しているのか疑問の声もある。外交は本来、国の専管事項であり、県が独自に取り組むことが果たして有効か。予算や人材を投じる以上、成果や県民への還元が明確でなければならない。これまでの取組の成果と課題をどう認識しているのか伺う。
(4) 南米には多くのウチナーンチュが移民として根を下ろし、沖縄との強固な絆を築いてきた。南米事務所の設立は、世界のウチナーンチュネットワークをさらに強化し、経済・文化・人的交流を促進する上で大きな意義を持つ。県として設立に向けた準備状況や課題をどう捉え、積極的に推進する意思があるのか伺う。
(5) 玉城知事はハワイを訪問したが、税金を使った公式出張である以上、成果を県民に説明する責任がある。経済交流や観光促進、人材育成など、どのような分野で具体的に成果を得たのか。出張の意義と成果を明確に示すべきではないか伺う。
(6) 池田副知事はカナダを訪問したが、その目的や成果についても十分な説明を行っていただく必要がある。県民が納得する成果がなければ、単なる慣例的な国際交流に終わりかねない。どの分野でどのような成果を上げたのか、県として今後の関係構築にどうつなげる考えなのか伺う。
(7) 2年後に開催予定の世界のウチナーンチュ大会は、世界中の同胞を結ぶ重要なイベントである。大会運営の準備状況や課題はどうか。財源確保、人材育成、地域連携を含め、成功に向けてどのような体制を整えているのか。知事の決意を伺う。
(8) 福建・沖縄友好会館は、平成10年に開館し27年が経過するが、現在の利用状況や財務の健全性、国内外企業の活用実績が不明確である。県が関与する施設として、どのような役割を果たしているのか。実態をどう把握し、今後の在り方をどう考えているのか伺う。
2:国土強靱化・防災減災・交通施策について
(1) 県内でも豊見城市で実証事業が展開されているライドシェア事業は、新たな移動手段として注目されている。過疎地や交通不便地域の移動課題を解決する可能性がある一方で、タクシー業界との競合や安全管理、運行ルールの整備など課題も多い。県はこの実証事業をどのように評価しているのか。公共交通体系の一部として導入を拡大する考えがあるのか伺う。
(2) 高速道路利用の効率化や渋滞解消に資するETCは全国的に普及が進んでいるが、沖縄では導入率が依然として低いと指摘されている。観光客の利用や物流効率化の観点からも普及促進は重要であり、インフラ整備や利用者支援策が求められる。県は現状の普及率をどう把握し、今後の普及促進に向けてどのような施策を講じるのか伺う。
(3) 全国的に水道管の破損や老朽化更新費用の増大が課題となる中、沖縄県でも耐震化計画が策定されている。離島を含め災害時のライフライン維持は喫緊の課題であり、更新事業を計画的に進める必要がある。企業局の平準化の取組や水道PPP/PFIの推進状況を県はどう認識しているのか。老朽化対策をどのように強化していくのか伺う。
(4) 県内の交通渋滞解消や観光振興に資するとされる鉄軌道構想は長年議論が続いているが、最大の課題は事業採算性にある。建設費用や利用者数の見込み、維持管理コストを冷静に見極める必要がある。県は現時点での採算性をどう分析し、実現に向けてどのような検討を行っているのか。事業化の可能性について伺う。
(5) 県内道路の老朽化や舗装の劣化、歩道の未整備、雑草繁茂は、交通安全や住民生活の質に直結している。限られた予算の中で維持管理の優先順位をどうつけるかが課題である。県は性能規定方式を採用しているが、現状の維持管理体制をどのように評価し、重要路線以外への対応も含めて住民の安全と利便性を確保するために、どのような改善策を取るのか伺う。
(6) 公共工事の入札不調や不落の背景には、資材高騰や労務単価との乖離がある。現実に即した適正な単価設定を行わなければ、必要な工事が遅れ、インフラ整備が滞るおそれがある。県は単価設定の在り方をどのように見直しているのか。土木建築予算の適正化について見解を伺う。
(7) 県は既に「次世代交通ビジョンおきなわ」を策定しているが、従来の総合交通体系基本計画との関係性が不明確との指摘がある。両計画をどのように位置づけ、整合性を確保しているのか。県として、交通体系全体をどのような方向に導こうとしているのか伺う。
(8) 特定利用空港・港湾の指定は、防災や物流拠点の強化に大きな意義がある、にもかかわらず、県内での整備は遅れている。離島の安全保障や災害対応の観点からも不可欠だが、次年度以降、県はどのような整備方針を描いているのか。具体的な計画を伺う。
(9) 那覇市中心部の与儀-開南間においては、交通渋滞緩和や公共交通優先の観点からバスレーン規制が設けられている。しかし近年は、利用状況や交通実態の変化により、住民や事業者から「過度の規制ではないか」との声も寄せられている。県はこの区間のバス規制の効果をどのように検証しているのか。利用実態に即した見直しを行う考えはあるのか伺う。
(10) 交通安全の基本となる道路標示は、老朽化や摩耗により視認性が低下している箇所も多く、夜間や雨天時に事故リスクを高めている。特に県道、国道の交差点では、更新の遅れが目立つとの指摘がある。県は道路標示の維持管理をどのように行っているのか。更新サイクルを定め、計画的に改善する考えがあるのか伺う。
(11) 沖縄本島をはじめ主要都市部では慢性的な交通渋滞が深刻化し、物流や観光、住民生活に大きな支障を及ぼしている。道路整備や交差点改良、バイパス新設などの施策が求められているが、事業の遅れが課題となっている。県は現在、どの道路整備事業を重点化しているのか。交通渋滞解消に向けた具体的方針を伺う。
(12) 沿岸部の低層地帯では、大規模地震や津波発生時における垂直避難先の不足が指摘されている。津波避難タワーの整備は住民の生命を守るために不可欠であり、義務づけの検討を求める声もある。県は現状の避難施設整備状況をどう把握しているのか。今後、避難タワー整備を計画的に進める考えがあるのか伺う。
(13) うるま市の石川赤崎交差点は交通量が多く、事故の危険性や渋滞が常態化している。県は一つの対策としてロータリー化の検討を進めているとされるが、地元住民からは抜本的な解決策を求める声も根強い。県はロータリー化の実現可能性をどう評価しているのか。また、安全性や利便性を高めるためにどのような改善を図ろうとしているのか伺う。
(14) 多くの離島を抱える沖縄において、災害時備蓄の確保は極めて重要である。現在、県が備蓄している食料や水、医薬品などはどの程度の量で、どのように配備されているのか。離島や僻地の住民に迅速に届く体制をどう確保しているのか。備蓄の実態と今後の改善方針について伺う。
(15) 山間部や離島などでは、テレビや携帯電話の電波が届きにくい地域が依然として存在し、災害時の情報伝達や住民生活に大きな支障を及ぼしている。難視聴・不感地帯の解消は安心・安全の確保に不可欠である。県は現状の把握をどう進め、国や通信事業者と連携して改善に取り組む考えがあるのか伺う。