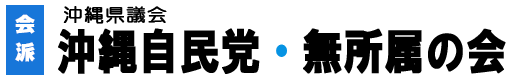[代表質問] 新里匠 令和7年第5回沖縄県議会9月定例会
令和七年9月18日(木)
第5回沖縄県議会(9月定例会)の代表質問に沖縄自民党・無所属の会より新里議員が3番手に立ちます。以下の質問項目を事前通告いたしました。

1:医療・介護・福祉・生活衛生について
(1)近年の物価高騰に加え、水道料金の値上げが県民生活に大きな影響を与えている。水道事業を所管する県や企業局においては、経営改善努力の限界や老朽化施設の更新費用の増大が背景にあるが、県民にとっては生活コストの直撃となっている。県は現状をどう分析し、料金高騰を抑えるためにどのような予算措置や経営支援を講じているのか伺う。
(2)高齢者を狙った特殊詐欺が後を絶たず、県内でも被害額が増加傾向にある。警察や自治体が注意喚起を行っているが、依然として防止には限界がある。金融機関や通信事業者との連携強化、最新技術を用いた防止策、地域での見守り体制など、多角的な取組が求められている。県は現状をどのように把握し、どのような総合対策を推進しているのか伺う。
(3)障がい者の社会参加や自立支援の一環としてスポーツの役割は大きく、特に車椅子ラグビー団体の活動は注目されている。今般、北海道大会への派遣費支援が課題となっていたようだが、県として障がい者スポーツの振興をどのように位置づけ、支援策をどのように講じていくのか。具体的に派遣費支援を含めた今後の方針を伺う。
(4)沖縄県の自殺率は依然として全国平均を上回る状況が続いており、特にうるま市では悲しい事案も発生した。背景には経済的困窮や孤立、精神的ケア不足など多様な要因があり、行政による支援の強化が求められている。県はこうした現状をどう受け止め、相談体制の拡充や地域連携強化など具体的にどのような自殺防止策を進めているのか伺う。
(5)年金収入のみで生活する低所得高齢者が増える中、家賃負担が重くのしかかり、住まいの確保が困難になっている。県はアパート支援事業を進めているが、対象者の拡充や支援内容の充実が求められている。住居の安定は高齢者の生活の基盤であり、福祉政策の根幹でもある。県は現状をどう評価し、事業の改善や強化をどのように進めるのか伺う。
(6)介護支援専門員(ケアマネージャー)は利用者にとって最も身近な存在であり、介護サービスの要となる役割を担っているが、その賃金は責任に比して低水準にとどまっている。県協会からは独自の処遇改善策を求める声が上がっているが、県は現状をどう認識しているのか。人材確保や介護の質向上の観点から、県独自の支援策を検討する意思があるか伺う。
(7)沖縄のエンゲル係数は全国的にも高水準であり、物価高や物流コストの高さが生活を圧迫している。さらに、保育や介護など公定価格に基づく職種では、地域の物価に比して賃金水準が低く、人材流出の要因となっている。診療報酬に地域加算があるように、介護や保育でも地域加算を導入すべきではないか。県は国に対して「南西諸島特別加算」のような制度を提案する考えがあるのか伺う。
(8)産後鬱や孤立感を抱える母親の増加が社会問題となっている。沖縄県内でも産後ケア事業や妊産婦支援が行われているが、市町村によって取組状況に差がある。母子の心身の健康を守るためには、柔軟で切れ目のない支援体制が不可欠である。県は現状をどう評価し、各市町村の取組格差を是正するためにどのような支援を進めていくのか伺う。
(9)北部地域における医療体制の拡充を目的として整備が進められている北部医療センターは、住民にとって待望の拠点病院である。救急医療や専門医療の提供体制の充実が期待されるが、工事進捗や人材確保、開院後の運営体制など課題も少なくない。県は整備の進捗状況をどのように評価し、課題解決にどう取り組んでいるのか伺う。
2:経済産業・地域活性化について
(1)米国の通商政策として導入されたトランプ関税は、日本企業にも大きな影響を与えており、特に輸出関連産業においてコスト増加や収益圧迫が懸念されている。沖縄県内企業も例外ではなく、製造業や輸出関連事業者に対する影響は無視できない規模となりつつある。県はこれまで企業への相談体制をどのように整備してきたのか。実際の相談件数や支援実績を含め、影響の実態把握と対応状況について伺う。
(2)近年、全国的に企業倒産が増加傾向にあり、その背景には人手不足が深刻な要因の一つとして挙げられている。沖縄県内においても、慢性的な人材不足や労働人口減少が企業経営に直結する事態が見られる。特に中小企業やサービス業においては、人材確保難が事業継続の妨げとなり、倒産や廃業を余儀なくされるケースが懸念される。県として倒産件数の現状をどう把握し、人手不足との関連をどう分析しているのか伺う。
(3)コロナ禍で実施されたゼロゼロ融資は多くの県内企業を支えたが、返済開始時期を迎えた今、返済負担により経営悪化が顕在化している。全国的にも倒産件数の増加が報じられており、沖縄でも同様のリスクが高まっている。県として、ゼロゼロ融資を受けた企業の経営状況をどのように把握しているのか。また、経営再建や事業継続を支えるための相談体制や支援策をどのように講じているのか伺う。
(4)沖縄県の最低賃金は今年度71円引き上げられ1023円となり、上昇率7%は過去に例を見ない規模である。物価高や人件費上昇に直面する中小企業にとっては大きな負担増であり、経営圧迫が深刻化している。県は今回の最低賃金引上げをどう受け止め、企業への影響をどのように把握しているのか。負担緩和策を検討しているのか伺う。
(5)東部海浜開発「潮乃森」事業は県東部エリアの将来像を左右する重要事業であり、観光拠点形成や地域活性化の核となる可能性を秘めている。長年にわたり課題が指摘されてきたが、事業推進の進捗や課題はどのように整理されているのか。県として地域住民や関係機関とどのように連携を図り、実現に向けた取組を進めているのか伺う。
(6)インボイス制度は、特に中小零細事業者に大きな負担を課している。制度対応のための事務作業やシステム投資が重くのしかかり、経営悪化や廃業の要因となるおそれがある。沖縄県内の中小企業における対応状況や課題をどう把握しているのか。制度が地域経済に及ぼす影響を県はどのように認識しているのか伺う。
(7)人口減少と少子高齢化の進行により、各産業分野で深刻な人材不足が顕在化している。その打開策の一つとして高齢者の活躍推進が注目されている。沖縄県内においてシルバー人材センターの活動はどのように展開されており、雇用や社会参加にどのような成果を上げているのか。今後の人材確保策としてどのように位置づけ、強化していくのか伺う。
(8)本年、沖縄を舞台とした映画「木の上の軍隊」や「宝島」が注目を集めている。映像コンテンツは観光資源としての効果も大きく、聖地巡礼型ツーリズムなど新たな可能性を広げる。国内での撮影は規制の壁もあり、海外での代替も行われているが、沖縄を舞台とする撮影環境整備は重要課題である。県は特区制度などを活用し、撮影規制やビザ取得緩和を含めた振興策を検討すべきではないか。
(9)老朽化が進む商工会館は中小企業の活動拠点として重要な役割を果たしている。安全性や機能性の観点から建て替えが課題となっているが、費用負担の大きさから単独での実現は難しい。県としてどのような支援策を検討しているのか。中小企業支援や地域経済活性化の観点からも、商工会館建て替えに対する県の支援の方向性を伺う。
3:農林水産行政について
(1) JAおきなわが鶏卵価格の公表を廃止したことは、農家や消費者にとって価格の透明性が失われる重大な問題である。市場価格の動向を把握できなければ農家の経営判断に影響し、消費者の生活にも直結する。県はこの公表廃止をどう受け止めているのか。今後、鶏卵流通の安定や価格の透明性確保のため、どのような対応を取るのか伺う。
(2)県内産米の価格は輸送コストや規模の小ささから全国平均に比べて割高となり、消費者や農家双方に影響している。特に物価高騰の中で、米価の動向は県民生活に直結する課題である。県は米価の現状をどう分析し、安定的な供給と価格抑制のためにどのような施策を進めているのか伺う。
(3)飼料高騰や燃料費増により、県内の酪農家は深刻な経営危機に直面している。牛乳の需給不安は県民生活に直結する問題でもある。県は酪農家の現状をどう把握しているのか。経営安定と生産継続のため、緊急支援や構造的な改善策をどう講じていくのか伺う。
(4)全国的な和牛需要は高い一方で、飼料価格や資材高騰によって繁殖農家の経営は逼迫している。沖縄における和牛繁殖は地域農業の基幹であり、後継者確保や生産維持が急務である。県は現状の厳しさをどう捉え、持続的な繁殖農家経営を支えるためにどのような支援策を検討しているのか伺う。
(5)沖縄の食文化に不可欠な豚肉を支える養豚業では、母豚導入支援を複数年にわたり求める声が上がっている。資金負担の大きさから経営継続に不安を抱える農家も少なくない。県は現状の要望をどう受け止め、養豚業の持続性確保に向けどのような支援策を講じていくのか伺う。
(6)ヤギ肉は需要が拡大しているが、近親交配の進行で遺伝的多様性が失われ、異常発生の増加が懸念されている。生産者からは優良ヤギの遺伝資源導入を求める声が高まっている。県は現状をどう把握し、持続的なヤギ生産のためにどのような支援を検討しているのか伺う。
(7)侵入害虫であるセグロウリミバエは農作物に深刻な被害を与えかねない。侵入防止と被害拡大防止には迅速な防除体制の構築が不可欠である。県は現状の対策をどう講じており、農家を守るために今後どのように防除体制を強化していくのか伺う。
(8)サトウキビは沖縄農業を代表する作物であり、製糖業と一体となって地域を支えている。しかし、台風被害や燃料費高騰により生産と経営が不安定化している。県は今年の生産状況と製糖業の現状をどう分析し、安定した産地維持のためにどのような方策を講じているのか伺う。
(9)老朽化が進む県内の製糖工場は、安全性や効率性の観点から早急な建て替えが求められている。地域の雇用や経済基盤にも直結する課題であり、放置すれば製糖業全体の持続可能性が揺らぐ。県は現状をどう把握し、建て替えや更新をどう進めようとしているのか伺う。
4:SDGs・環境行政について
(1)水素社会実現に向けた取組が全国的に進められているが、沖縄では水素ステーションの設置が依然として遅れている。観光立県として持続可能なエネルギー基盤の整備は喫緊の課題であり、脱炭素や災害時のエネルギー確保にも直結する。県は現状の整備状況をどう認識しているのか。今後、導入を促進する具体策をどう描いているのか伺う。
(2)脱炭素社会の推進に向け、電気自動車の普及が全国的に進められているが、沖縄では充電インフラ不足が大きな障害となっている。特に観光地や離島では、利便性の低さが普及の妨げとなりかねない。県は現状をどう把握し、どのように整備を拡充する計画か。EV普及促進の観点から方針を伺う。
(3) 国立自然史博物館は国内外から多くの来訪者を呼び込む可能性を秘め、教育・研究・観光の拠点となり得る。沖縄の生物多様性や自然環境の特性を生かす絶好の機会だが、誘致競争も想定される。県は誘致の可能性をどう捉えているのか。計画の具体化に向けた準備を進める考えがあるのか伺う。
(4)県内各地で松くい虫被害が深刻化し、景観や生態系への影響が広がっている。特に久米島では「五枝の松」が枯死の危機に瀕しており、文化的・観光的損失が大きい。防除対策や被害拡大防止のための予算措置が求められるが、県は現状をどう認識し、今後どのように取り組むのか伺う。
(5)県内のソテツ資源は景観や観光、文化にとって重要であるが、カイガラムシによる被害が拡大するおそれが強まっている。侵入防止と防除の両面での対応が必要だが、県は現状をどのように把握し、具体的にどのような対策を講じるのか伺う。
(6)県内港湾や漁港、マリーナには持ち主不明の放置船が多数存在し、景観や航行の安全を損ね、防災面でも危険を伴う。法制度の限界も指摘されており、撤去・処分の体制整備が求められる。県は現状をどう把握し、放置船対策をどのように進める考えか伺う。